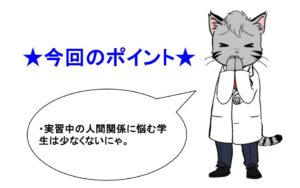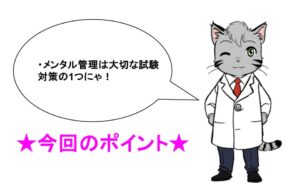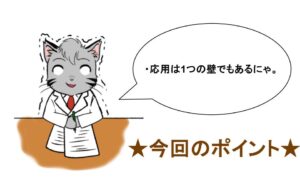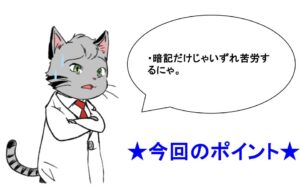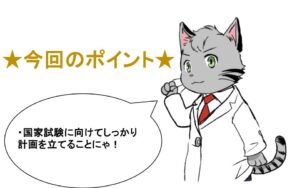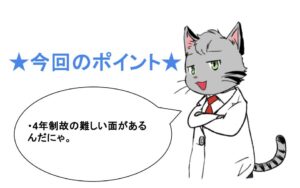薬学部生の留年率の増加と定員割れの関係について

近年、薬学部生の留年率の増加が話題になっています。
今回は留年率増加の原因と、大きな原因の1つである「薬学部の定員割れ」の関係について紹介をしていきます。
どんな関係があるのかぜひ予想しながら読んでみてください。
薬学部急増とその背景
「薬学部」のある大学は2006年以前が50校だったのに対し、現在は約80校に増えています。
その背景をみていきましょう。
薬学教育6年制への移行(2006年度)
2006年、薬剤師の専門性を強化するために薬学教育が4年制から6年制に移行しました。
これに伴い、薬剤師の役割が調剤だけでなく、医療現場での薬物治療の管理やチーム医療への参加など、それまでよりも高度で専門的なものへと変化しました。
この影響で薬剤師の役割自体が増えることになります。
その結果として薬剤師の需要がさらに高まると見込まれ、多くの大学で薬学部の新設が進められるようになりました。
薬剤師需要の増加予測
少子高齢化が進む中で、高齢者向けの調剤薬局や医療機関での薬剤師の需要が増加すると予想されました。
特に地域医療における薬剤師の重要性が強調され、薬学部の拡大が奨励されていました。
大学経営の多角化と収益性
私立大学を中心に大学経営の安定化を目指して薬学部が次々と新設されました。
薬学部は他の学部に比べて学費が高額(6年間で1,000万円以上)であり、収益性の高い学部として注目をされていました。
このような経営的観点からも薬学部の急増が後押しされたと考えられています。
薬学部急増の現状
薬学部の数と定員の増加
日本国内の薬学部は、6年制導入前の約50校程度から、現在では80校以上に増加しています。
入学定員も2006年度以前に比べて約2倍(10,000人以上)に拡大しました。
新設校の特徴
薬学部の新設は、地方私立大学を中心に行われており、地域医療に貢献する人材の育成を目指す大学も多いです。
しかし、新設校の多くが全国的な知名度を持たないため、受験生の獲得に苦戦しているケースも少なくありません。
薬学部の急増による影響と課題
薬学部間の競争激化
薬学部の増加により、全国の大学間で生徒を獲得するための競争が激化しています。
特に次のようなの課題が浮き彫りになっています
「都市部vs地方」
都市部の有名大学に志願者が集中する一方、地方の薬学部では定員割れが起こりやすい状況です。
「国家試験合格率」
薬剤師国家試験の合格率が大学ごとに異なるため、合格率の高い大学への志願者集中が進んでいます。
教育の質の維持
薬学部の急増に伴い、教育の質が十分に確保されているかという課題もあります。
新設校では施設や教員の確保が不十分な場合もあり、薬学教育の質に影響を及ぼす可能性があります。
一部の大学では、進級や卒業の基準が厳しく、留年率が高いことが問題となっています。
薬剤師の供給過剰の懸念
薬学部の拡大により、薬剤師の供給が需要を上回る懸念も出ています。
特に都市部では薬剤師が飽和状態となり、就職が難しくなる一方、地方や僻地では薬剤師が依然として不足しているという地域間の偏在が課題です。
今後の展望と必要な取り組み
薬学部の急増が引き起こした課題を解決するため、次のような取り組みが必要だと考えます。
定員の適正化
全国の薬学部の入学定員を見直し、地域や需要に応じた適正な規模へと調整することが重要です。
地域医療への貢献
地方の薬学部では地域医療に貢献する薬剤師の育成を目指した教育プログラムを充実させることで、志願者を集める努力が求められます。
薬剤師の新たな役割の創出
調剤業務にとどまらず、在宅医療や予防医療など、薬剤師が活躍できる新たな分野を開拓することが薬学部の志願者増加につながるかもしれません。
「定員割れと留年率増加の関係」まとめ
薬学部の定員割れによって「大学側の定員の確保」が難しくなり、入学までのボーダーラインがこれまでよりも下がっていることが伺えます。
そのため、ギリギリの点数で入学した生徒は入学後に学力が足りず、留年や単位の取得に苦労してしまうことが考えられます。
留年を回避するには早めの勉強スタートが大切です。

「薬剤師の需要」も変化している
薬剤師の需要は、2000年代には急速に高まっていましたが、現在では次3つのような変化が起きています。
①都市部での薬剤師の飽和
都市部では薬局やドラッグストアでの薬剤師採用が飽和状態になりつつあります。
また、一部地域では薬剤師の求人倍率が低下し、給与や就業条件の伸びが鈍化しています。
これにより「薬剤師は就職に困らない」というイメージが薄れつつあります。
②地方での薬剤師不足
都市部での薬剤師が飽和傾向にある一方で、地方や僻地では依然として薬剤師が不足しており、地域間での需要に大きな偏りがあります。
しかし、学生の地方勤務への志向が低く、このことが薬剤師需要の不均衡を悪化させています。
➂医療現場での役割の変化
調剤業務が自動化・効率化される一方で、薬剤師には患者の薬物治療や服薬指導の支援といった、より高度なスキルが求められています。
これにより、新たなスキルを学ぶ負担が増加している点も、受験生にとって心理的なハードルとなっている可能性があります。
薬剤師需要の変化がもたらす影響
薬学部の魅力の低下
薬剤師需要が飽和気味であるという認識が広まることで、受験生にとって薬学部の魅力が低下しています。
特に学費が高く6年間の長い学習期間を必要とする薬学部は、コストパフォーマンスが悪いと感じる受験生も少なくありません。
進路選択の多様化
受験生の間では、薬剤師以外の医療系職種(看護師、臨床工学技士、理学療法士など)や理系学部(理学部・工学部)への志向が高まっています。
これらの分野では4年間で学位を取得できることや、比較的低コストで学べる点が魅力となっています。
地域間格差の拡大
都市部の薬学部では人気が維持されている一方、地方や新設の薬学部では志願者数が減少し、定員割れが深刻化しています。
地域ごとの薬剤師需要の変化が、大学選びに直接影響していると考えられます。
定員割れには少子化も影響も
少子化による受験生の減少
少子化の進展により、大学全体の受験生数が減少しています。
薬学部の定員は2006年の6年制移行以降に大幅に増えたため、定員数が受験生の総数に対して過剰になっています。
大学間競争の激化
少子化の影響で、大学間で受験生を獲得する競争が激化しています。
国家試験合格率や進級率が低い大学、新設校、地方校は受験生に敬遠される傾向が強まっています。
志願者数減少への対応と今後の課題
薬剤師の役割拡大による魅力向上
薬剤師が調剤だけでなく、在宅医療や予防医療、薬物治療のコンサルティングといった新しい分野で活躍することが期待されています。
こうした薬剤師の可能性を広くアピールすることで「薬学部を卒業した後の働き方」の魅力を高めることが重要です。
教育の質の向上
各大学が国家試験合格率を向上させるためのカリキュラム強化や、進級支援の充実に取り組むことが求められます。
学生にとって学びやすく、成果が出やすい環境を整えることで志願者数の減少に歯止めをかけられる可能性があります。
地域医療に特化した取り組み
地方薬学部では地域医療に貢献する人材を育成するプログラムを導入し、地域密着型の教育を進めることで独自性を打ち出す必要があります。
進学コストの軽減
高額な学費が受験生を敬遠させる要因の一つです。
奨学金制度や学費減免制度を拡充し、経済的負担を軽減する取り組みが重要です。
まとめ
薬学部の志願者数の減少は、「薬学部を持つ大学の増加」「薬剤師需要の変化」「少子化」の3つの要素が密接に関係しています。
都市部での薬剤師の飽和や、調剤業務の効率化、進路選択の多様化が薬学部の魅力を相対的に低下させているのが現状で、「卒業後も安定ではないのかも」と感じる原因はこの部分が大きいでしょう。
その一方で、高齢化社会や地域医療の重要性を背景に、薬剤師には新たな役割が期待されています。