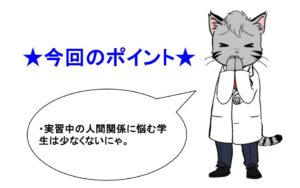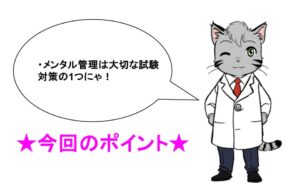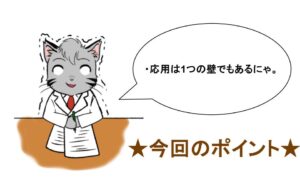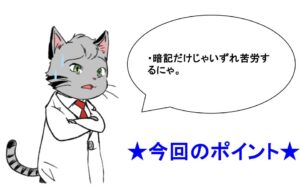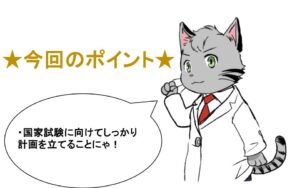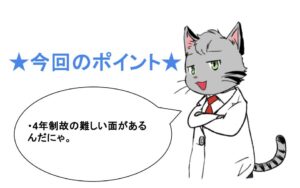薬学生向け!燃え尽き症候群を避けるためのセルフケア術!
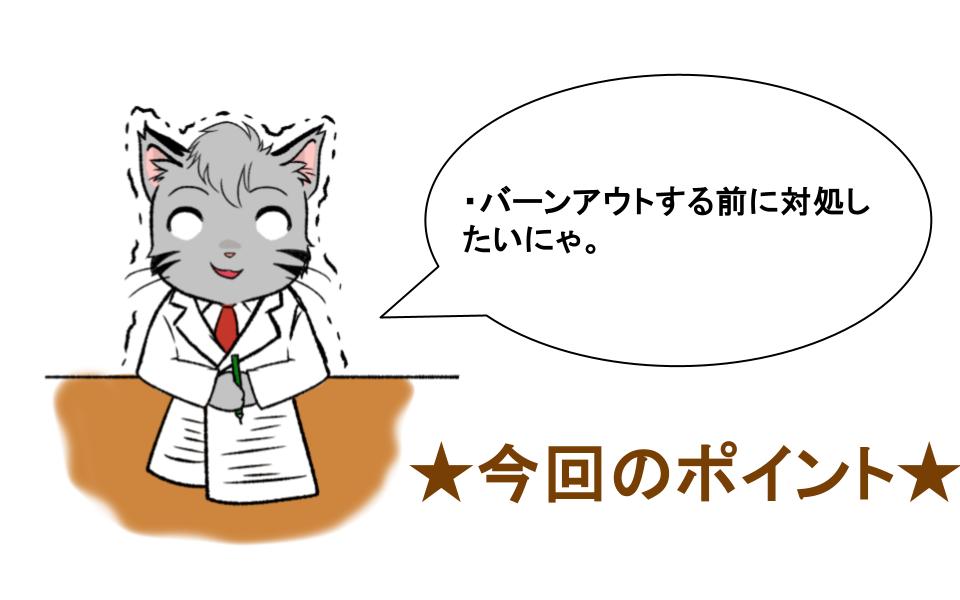
大学生の多くは真面目に勉強に取り組んでいます。
その真面目さが健康的であればいいのですが、’’頑張りすぎている’’ 状態では残念ながらデメリットも出てきます。
勉強熱心な学生が多い薬学部は特にそうで、燃え尽き症候群になっている人は決して珍しくありません。
今日は、そんな大学薬学部の学生に向けて、燃え尽き症候群を避けるためのセルフケア術についてご紹介します。
【そもそも「燃え尽き症候群」とは?】
あなたもおそらくこの言葉は聞いたことがあるでしょう。
大学生における燃え尽き症候群は、勉強の頑張りすぎによって、急に勉強へのやる気が低下したり、授業に行きたくない、教科書自体も見たくない、などの学習への意欲を失ってしまう状態のことです。
燃え尽き症候群は何も甘えではなく、一生懸命勉強をする学生であれば誰でも起こり得ます。
大学では、普段の授業に加え、レポート作成、研究や実験、試験など様々なイベントがあり、それらに向けて勉強をします。
行っている最中は交感神経が活発になっていますし、やる気に満ち溢れていますので、どんどん進みますが、ある時、急に又は終わった後などにこの症状が出てきます。
述べた通り、
・勉強したくない
・勉強部屋を見たくない
・大学に行きたくない
・好きだった薬学も嫌
など、学習への意欲が急激に、且ついきなり落ちてしまいます。
【燃え尽き症候群を避けるためのセルフケア術】
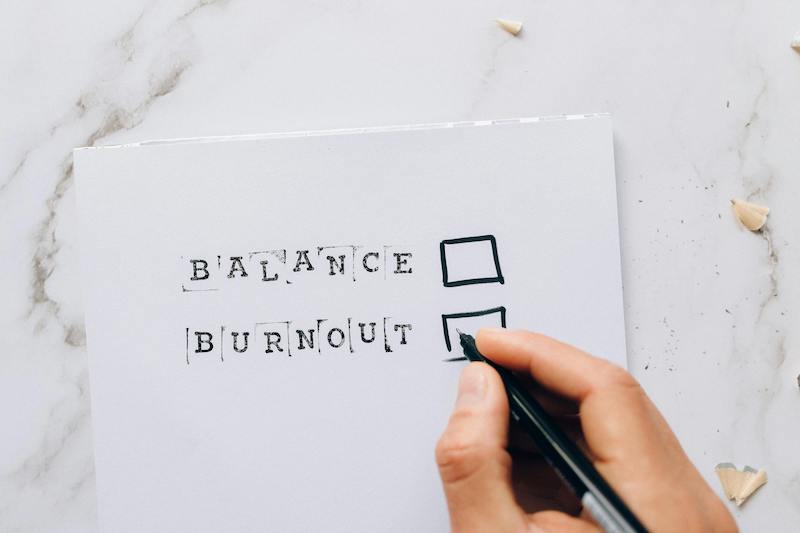
大学薬学部の学生は、勉強量が多く難しい学部を選んでいますので、勉強への意欲は元々高いはずです。
そのため、この燃え尽き症候群になることがあるのです。
学生ができることは、それを未然に防ぐこと、そのための方法を順番に解説します。
≪友人と勉強する≫
大学では、食堂などでグループで勉強をしている人がいると思います。
実はこれは燃え尽き症候群を避けるためにも有効な手段です。
誰かと勉強時間を共有することで、1人で勉強することで感じる孤独感を避けることができます。
1人だとたまに「なぜこんな勉強をしているのか」「何のための勉強か」など、不安感などが出てきてしまうことがあります。
誰かと一緒ですので、困った時の相談もできます。
≪休む時は休む≫
要は、勉強をする時と休む時のメリハリをつけるということです。
ずっと勉強に時間を費やすからガス欠してしまうわけで、休憩をする時は勉強のことを忘れて休むことでメンタル面がリフレッシュできます。
スポーツをしてもいいですし、友人とプライベートを楽しんでもいいです。
また、勉強中の休憩でも同じ考えでOK。
1時間集中したら10分休む、など時間を管理します。
休む際は勉強場所から離れるようにしてください。
≪勉強を追い込む前にやめる≫
勉強をした後に、何もしたくなくなるくらい疲れ切ったことがあると思います。
もう脳も体もぐったりで、これは黄色信号でもあります。
余力を残して勉強をすることで、明日以降への体力の温存にもなります。
8割くらい勉強をして、体力が少し余っている状態で休むのが時にいいでしょう。
≪相談先を把握しておく≫
いくら気をつけても燃え尽き症候群になってしまったり、一歩手前という状態になることはあります。
そこで自分で対処できたらいいですが、難しいのが現状です。
そのために相談できる相手や場所を事前に見つけておくのが有効です。
例えば、家族や友人、先輩、大学の教務課や教授、その他、オンラインなどでもサービスがあるでしょう。
それだけでも、「困ったらここに相談すればいい」と安心感につながります。
【まとめ】
今日は、大学薬学部の学生に向けて燃え尽き症候群について解説しました。
できるだけ避けたいものであり、薬学部の学生はなりやすいともいえます。
時に自分を甘やかすことも忘れないようにしてください。