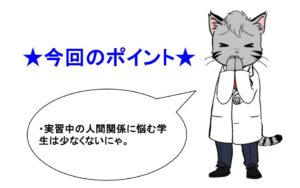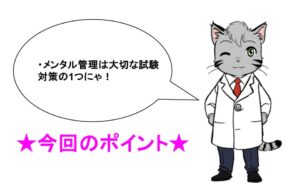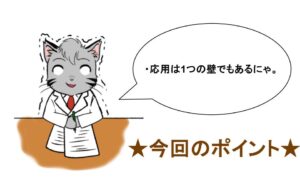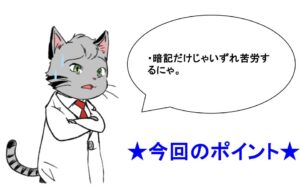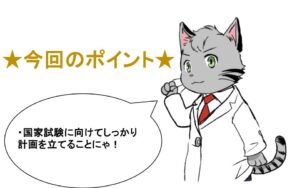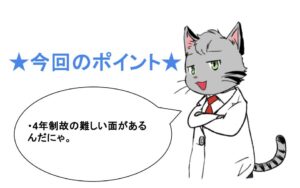薬学部で特に大変な学年
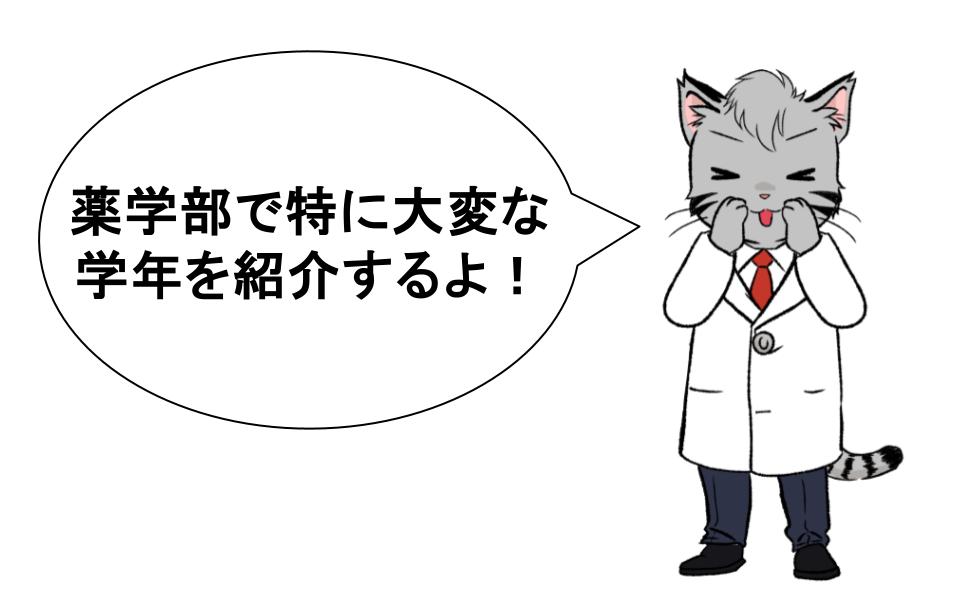
薬学部の学生生活は、とにかく勉強が大変です。
膨大な量の学習や実習に追われる毎日で、「6年間もつかな…」と不安になる学生も少なくありません。
他の学部と比べても専門性が高く、卒業後に控える国家試験に向けて、幅広い知識をコツコツ積み上げていく必要があります。
そのため、計画的に学習を進めることが欠かせません。
そうは言っても、薬学部の中でも「特にこの学年がしんどい!」という時期があるんです。
今回は、そんな学生たちが「大変だ」と感じる学年にスポットを当て、その理由や特徴について掘り下げてみます。
学年ごとに何が大変なのかを知ろう
「2年生」基礎科目とその応用が大変
薬学部の2年生は、基礎科目の学習が本格化する時期で、特に多くの学生が「難しい」と感じる学年です。
化学(有機化学・無機化学)、生物学、生化学、分析化学などの科目が本格的に始まります。
それらを理解するためには、高校時代の知識をさらに深めた学習が必要です。
また、1年生で習った基礎科目の知識がベースになることも多いため、1年生の単位をギリギリで取得した学生、課題や再試などの救済措置でなんとか単位を取れた学生にとっても苦しくなることが多いです。
これらの科目は3年生以降の専門科目や実習に直結しているため、この段階で理解が不十分だと後々苦労することになります。
さらに、薬学部の試験は内容が細かく、一度に複数の科目が重なることが多いため、試験期間中は膨大な範囲を一気に復習しなければなりません。
このように、2年生は今後の薬学部の学習の「土台」を作る年次であるため、特に大変だと感じる学生が多いです。
「3年生」専門科目と実験が本格化
3年生は薬学部の中で「中間地点」にあたる学年で、基礎から応用へと学びの内容が移行する時期です。
この段階では薬理学、病態生理学、製剤学といった専門性の高い科目が加わり、科目ごとの連携を理解する必要が出てきます。
これまでに学んだ基礎知識を応用する能力が求められるため、単なる暗記だけでは対応できず、「なぜこうなるのか」を深く考える力が必要です。
また、実験科目が本格的に始まるのもこの学年の特徴です。
実験には事前の予習や手順の理解、実験後のレポート作成が求められ、勉強の負担が増えます。
特に、レポートの完成度が評価に直結するため、細部まで気を配る必要があり、これが時間と労力を要する原因となります。
「5年生」実習と座学の並行
薬学部の5年生は、実務実習が中心となる学年で、多くの学生が「体力的に厳しい」と感じる時期です。
この年次では、病院や薬局での長期実習が始まり、学内での座学と並行して実務経験を積むことになります。
実習はフルタイムで行われるため、これまでのように自由に勉強時間を確保することが難しくなります。
さらに、実務実習では現場の薬剤師や患者さんと接するため、専門知識だけでなく、コミュニケーション能力や実務スキルも求められます。
事前学習や実習中の課題、振り返りレポートなど、実習に関連するタスクも膨大で、勉強と実務のバランスを取るのが非常に難しいです。
また、実務実習では「現場の責任感」を意識する必要があるため、精神的なプレッシャーも大きいのが特徴です。
このプレッシャーと多忙さが重なり、5年生を「特に体力的に大変な学年」と感じる学生は多いです。
「6年生」国家試験への追い込み
薬学部の最終学年である6年生は、薬剤師国家試験への準備が中心となる時期です。
この学年では、卒業研究や課題の提出がある場合もありますが、何よりも国家試験合格を目指した勉強が優先されます。
試験範囲は非常に広く、薬理学、製剤学、病態生理学などの膨大な知識を総復習する必要があります。
国家試験は問題数が多く、暗記だけでなく理解力や応用力が試されるため、試験勉強は計画的に進めなければなりません。
6年間の学びをすべて復習する負担は非常に大きく、さらに試験が近づくにつれてプレッシャーが増すため、多くの学生が精神的にも追い込まれる時期となります。
学年ごとに異なる大変さ
薬学部の学年ごとの大変さは、それぞれの段階で学ぶ内容や求められるスキルに応じて異なります。
特に、2年生は基礎科目の負担が大きく、3年生は応用的な学びと実験の両立、5年生は実務実習、6年生は国家試験というように、各学年で異なる苦労があります。
どの学年でも共通して重要なのは、計画的な学習と効率的な時間管理です。
特に大変な学年では、周囲のサポートや仲間と協力しながら、無理のないペースで進めることが、乗り越えるための鍵となるでしょう。
特に「留年が多い」といわれる学年
ここまでの内容だと「薬学部はどの学年も大変」となってしまいます。
しかし、この記事を読んでいる人は「特に」難しい学年はいつなのかを知りたいと思います。
「難しさ」「大変さ」は人によっても変わるため、ここでは「留年のしやすさ」に注目して掘り下げていきたいと思います。
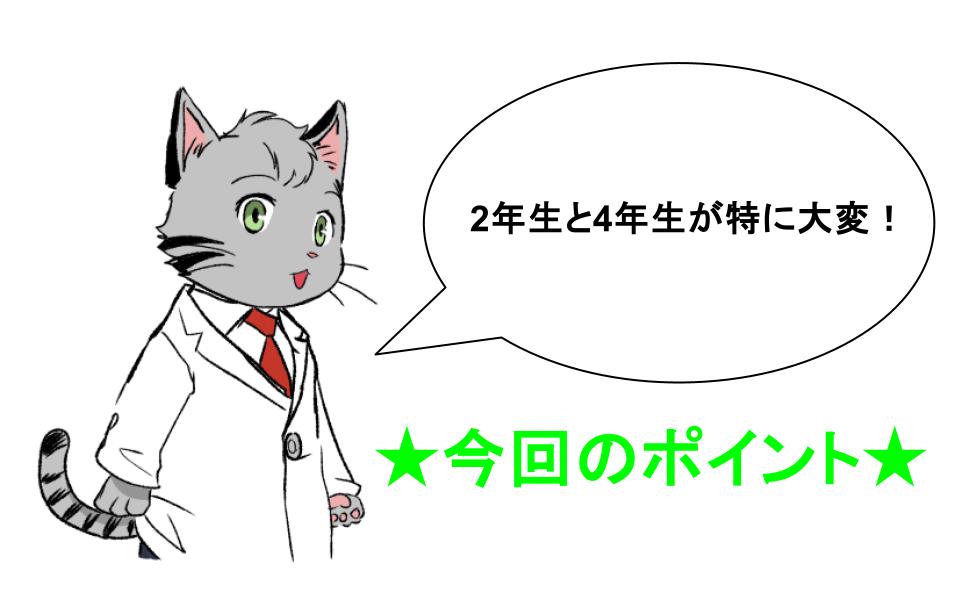
特に留年しやすいのは「2年生」と「4年生」
薬学部で特に留年が多いとされるのは、2年生と4年生です。
この2つの学年で留年が多くなる理由について、詳しく説明します。
「2年生」
薬学部の1年生では、生物学、化学、物理学といった基礎科目が中心となります。
これが2年生になると、これらの基礎をもとにした専門科目(薬理学や薬物動態学など)が本格的に始まります。
このタイミングで多くの薬学部生は以下のような勉強の壁に直面します。
専門科目の難易度が上がる
2年生で初めて専門的な内容に取り組むため、基礎知識が不十分だとつまずきやすくなります。
1年生の 基礎科目の知識が求められる
2年生の専門科目は、1年生で学んだ基礎知識が土台となります。
1年生の内容がしっかり理解できていないと、授業内容についていくのが難しくなります。
「4年生」
薬学部での留年が特に多いのは4年生で、この学年は「進級試験」や「共用試験(CBT・OSCE)」など、進級や実務実習に必要な重要な試験が課されるためです。4年生では以下のような要因で留年リスクが高まります。
共用試験(CBT・OSCE)の合格が必須
4年生では、全国統一のCBT(Computer-Based Testing)やOSCE(Objective Structured Clinical Examination)に合格しなければ実習に進めません。
この共用試験は薬剤師国家試験の基礎ともなる内容で、難易度が高いため、苦戦する学生が多くいます。
実習のための学力が求められる
4年生までに学んだ知識を確実に理解し、実践的に応用できるレベルが求められます。
理解が浅いまま進級してきた場合、4年生でその弱点が明確になることが多く、進級試験に影響します。
「推薦入学」の学生は「1年生」が大きなポイント
推薦入学で薬学部に入学した学生にとって、1年生の科目は特に単位を落としやすいとされています。
高校までの成績や活動実績が評価されて入学しているため、必ずしも受験勉強で徹底的に基礎科目を学んできたとは限らないことが理由の一つです。
薬学部の1年生では、化学や生物学、物理学といった基礎科目がカリキュラムの中心ですが、これらは薬学の専門科目を学ぶための土台となる重要な内容です。
高校時代に理科科目を選択していなかった場合や、基礎が十分に固まっていない場合には、授業についていくのが難しく、試験やレポートで思うような成績が取れないことが少なくありません。
また、推薦入学の学生は、高校時代に受験による厳しい勉強習慣が身についていないケースも多く、大学での学習量の多さに戸惑うこともあります。
そのため、早い段階から勉強のリズムを整え、基礎の復習に力を入れることが、1年生での単位取得に向けて重要です。
悩んだら「無料学習相談」をご利用ください
薬学部は他の学部に比べて学業の難易度が高く、6年制のカリキュラムによって留年率も高くなりがちです。
しかし、適切なサポートと計画的な学習を行えば、留年を回避することは十分に可能です。
大学側の支援を活用し、学生自身も工夫しながら学習に取り組むことで、進級や国家試験合格のハードルを乗り越えることができるでしょう。
また、外部のサポートとして、塾や予備校を活用するのも一つの有効な手段です。
薬学部生向けの専門的な指導を受けることで、理解を深め、効率よく試験対策を行うことができます。
自分の弱点を補強し、確実に進級・合格を目指すために、塾を検討するのも一つの選択肢です。
猫の手ゼミナールでは毎年多くの薬学部生の単位取得をサポートしています。
今の成績や学力に不安がある方は「無料学習相談」にてご相談ください。