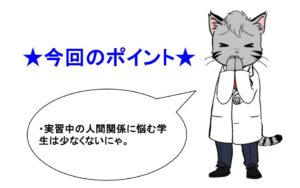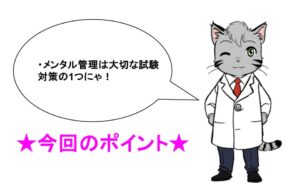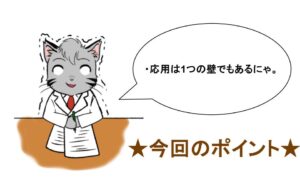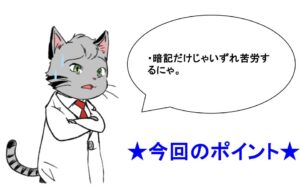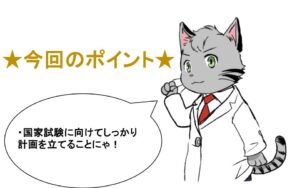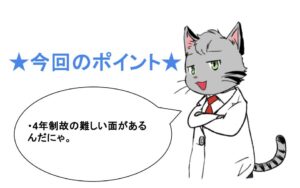【大学】4年制の薬学部卒でも薬剤師になれる?
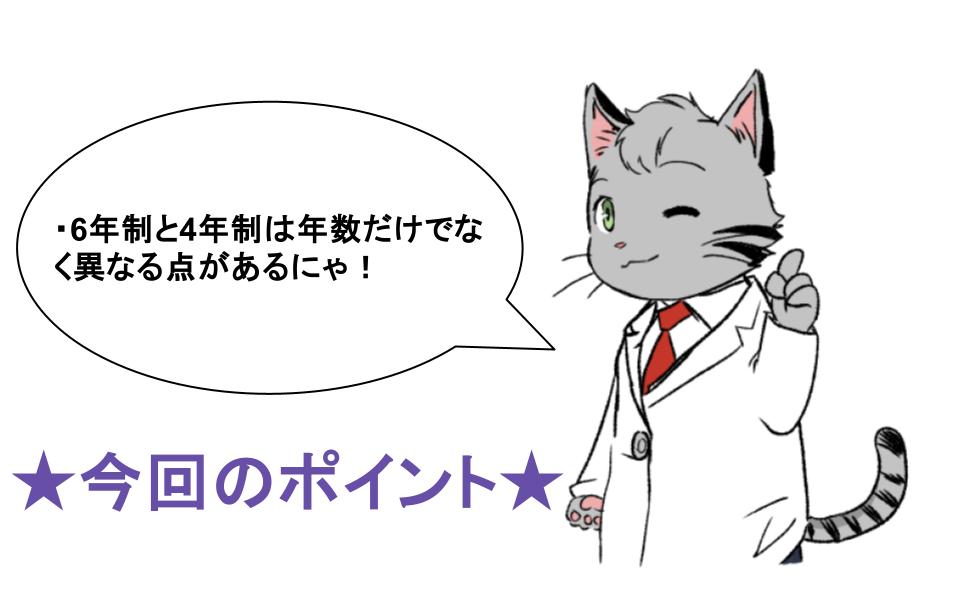
日本国内の大学薬学部には、6年制とこの4年制があります。
年数が異なるだけでなく、学ぶ内容や目的、就職先なども両者、異なるわけですが、学生やその保護者の方の中には、4年制の薬学部でも薬剤師になられるのか気になる人はいるかもしれません。
今日は、4年制の薬学部に関する内容、そして薬剤師になられるかについてご紹介します。
ぜひ最後までお読みください。
【薬剤師になるには6年制薬学部に行く必要がある】
さっそく、本日の結論にはなりますが、大学を出てから薬剤師になろうと思うと、6年制の薬学部に行く必要があります
そのため、この4年制の薬学部では薬剤師になることはできません。
2006年までは薬学部は4年制だったのが、その年から学校教育法の一部が改正されたことで、薬剤師を目指す場合は6年間の教育を受けることが義務付けられました。
つまり、4年制の薬学部では、薬剤師の国家試験の受験資格を取得できないということです。
≪6年制薬学部が必須になった理由≫
なぜ6年制になったのか?
その大きな理由として、薬剤師に求められるスキルや能力の多様化が挙げられます。
従来のような医薬品の調剤や管理業務だけでなく、現在ではチーム医療が推進されるようになっており、医療への関わりが強く求められるようになりました。
そのために必要なスキルをこれまでの4年間で学べるのか、それが疑問になり、制度が変わったというわけです。
では、何のために4年制の薬学部があるのか?
そこではどのようなことを学ぶ?
いろいろ気になる点があるでしょう。
【大学4年制の薬学部で学ぶこと】

この4年制の薬学部では、主に研究者の養成がゴールになります。
医療現場だけが薬学の知識を必要としているわけではなく、例えば、製薬会社の研究室、大学の講師や研究者などもその専門知識が必須になります。
薬学の研究者を輩出することで、世の薬学レベルを何段階も上げてくれることを期待されています。
4年制の薬学部では、薬剤師を目指すことがゴールではないので、それにかける勉強や共用試験対策、また実務実習への参加も必要ありません。
それらの時間をカットし、研究や実験に多くの時間を費やし、集中できるのが4年制薬学部の大きなメリットです。
≪研究者を目指すなら大学院に行くべき≫
仮に、4年間で卒業をして、研究者になりたいと思っても、実際はそう簡単ではありません。
研究者になる多くの薬学部生は、卒業後に大学院に進学し、修士課程以上を目指します。
そうでないと、製薬会社などの研究職に就くのは難しいのです。
なお、2017年までは4年制の薬学部を出てもその後大学院に進むことで、薬剤師国家試験の受験資格を得られましたが、今ではそれは廃止されています。
【まとめ】
いかがでしたか?今日は、4年制の大学薬学部に関する内容でした。
4年間で、薬学を学び、研究に時間を費やすことで、薬学という学問の将来の発展に貢献します。
では、本日も最後までお読みいただきありがとうございました。