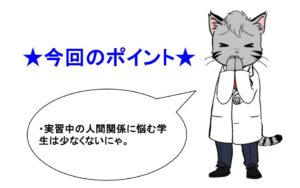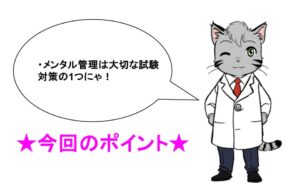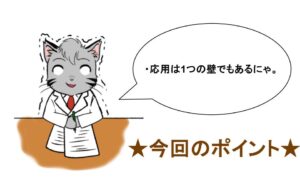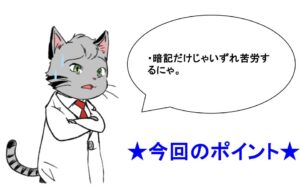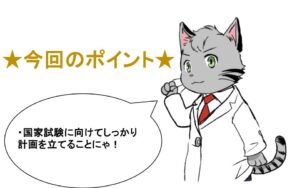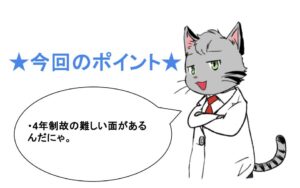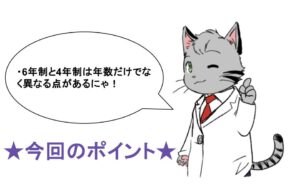大学6年制と4年制薬学部、世界の薬学部の状況
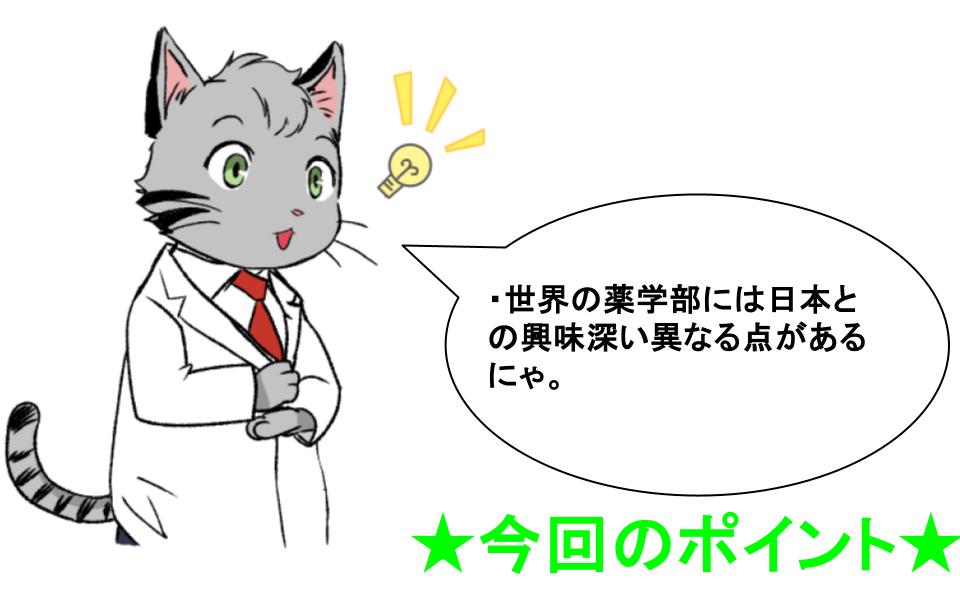
現在、大学の薬学部には6年制と4年制がありますが、薬剤師になるためには前者の6年制を選ばなければいけません。
以前、2006年までは4年制であっても薬剤師免許の取得は可能でしたが、学校教育法と薬剤師法が改正されたことで制度が変更になりました。
このように6年制と4年制の薬学部というのは、何も日本国内だけでなく世界的にも採用されているシステムになります。
今日は、世界の薬学部の状況や6年制と4年制の薬学部のシステムの違いなどについて詳しく見ていきましょう。
本記事はこちらの「文部科学省令和3年度大学における医療人養成の在り方に関する調査研究」の情報を参考にしています。
【世界の大学6年制と4年制薬学部の状況】
述べた通り、日本では大学6年制と4年制の薬学部があり、簡単に説明をすると、前者は薬剤師になるため、後者は研究職に就くため、と表現できます。
もちろん、6年制でも薬剤師にならない学生はいますし、4年制を出てから大学院に進む人もいます。
日本国内では、このような捉え方をされていますが、世界ではどうでしょうか。
基本的には、同じような考え方で、例えば、アメリカでは、州によって異なるので一概にはいえませんが、まず大学で2~3年で一般教育を学び、その後、大学院にて4年間学びます。
つまり、合計で6~7年ほどの時間が必要になります。
また、アメリカでは一般的に高校を卒業してからすぐに大学の薬学部に入学することはできず、一般教育、基礎学力を習得するために述べた通り、まず2~3年学びます。
これが日本でいう「大学」です。
その後、4年間を薬学部で学ぶのですが、これが日本でいう「大学」。
≪イギリスは基本的に4年間≫
欧州のイギリスでは、薬学部は基本的に4年間になっています。
ここには、教養科目は含まれていないことが多く、学士課程に加えて実務実習も含みます。
生物学、薬理学、経済学、倫理学など幅広い学問を学び、1年間の実務実習があります。
卒業をすると、修士号を取得できます。
【日本と海外の薬学部での学び方の違い】

日本の大学では、薬学部であってもまず、1年生や2年生で教養科目を学びます。
これは必ずしも薬学に関わるものではなく、学生として理解しておくべき一般教養ですが、その後に専門科目である薬学に関することを学ぶのが一般的です。
しかし、これは日本特有であり、海外では、必ずしもそうではありません。
先に述べた通り、アメリカなど北米ではいきなり薬学部に入学するのではなく、まず教養科目を学ぶ、そして欧州でも教養科目は高等学校で行われるのが普通です。
薬学に関係なくですが、基本的に大学に教養科目はなく、入学してからすぐに専門科目がスタートします。
≪日本のカリキュラム設定は基礎から専門へ≫
また、薬学部におけるカリキュラムの設定も日本と欧米諸国では大きく異なります。
日本では、やはりまずは基礎を学び、徐々に専門分野にうつっていくという流れですが、海外では、統合型教育を採用しています。
これはつまり、4年間で薬剤師に求められる資質から逆算して考え、必要な科目を設定しているのです。
基礎からの積み上げか、バックキャストして科目を設定・配置するか、どちらがいいと思いますか。
【まとめ】
今日は、大学薬学部に関する内容でした。
世界的に見ると、同じ薬学部でもいろんな学び方があり、非常に興味深いものです。
当サイトでは、このように大学薬学部の学生に向けて、学習に関する有益な情報を毎月発信していますので、ぜひ参考にしてください。