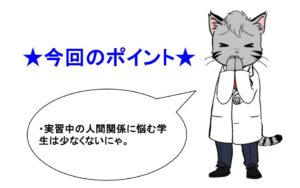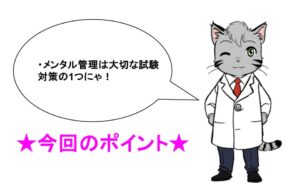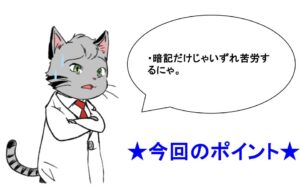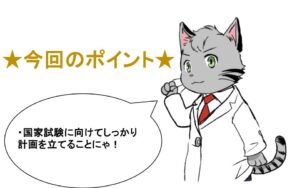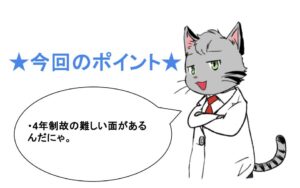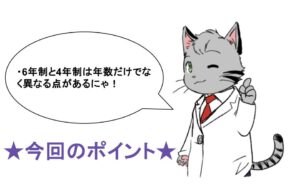薬剤師国家試験の過去問は解けるが応用に対応できない
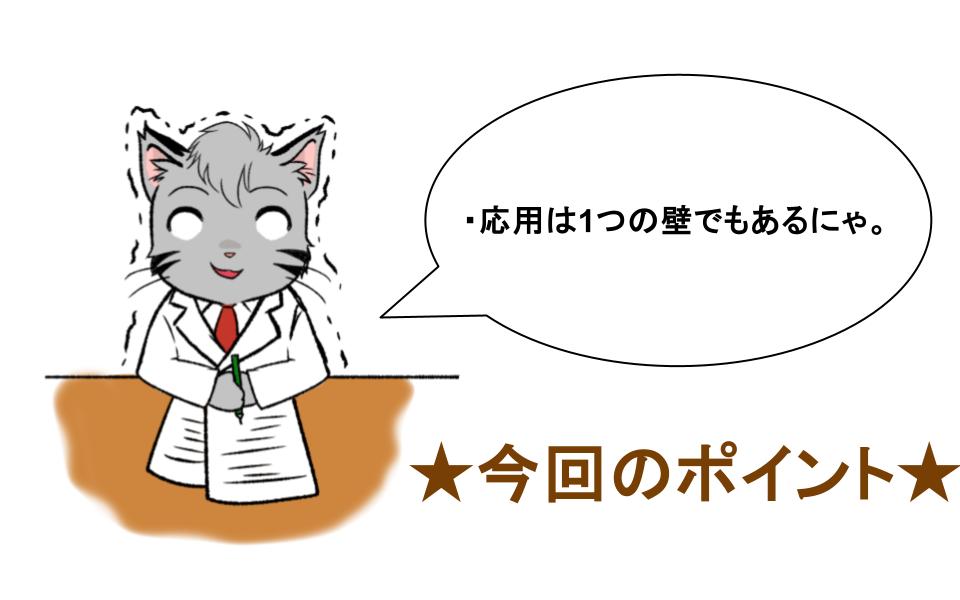
薬剤師国家試験の対策をする中で、よくあるのがこの過去問は解けても応用に対応できないというものです。
大学受験などの勉強でも同じようなことがあったかもしれませんが、これでは十分な点数は取られないかもしれません。
今日は、大学薬学部の学生に向けて、薬剤師国家試験について取り上げます。
【薬剤師国家試験の過去問利用は超重要】
まず、薬剤師国家試験を控える学生は、過去問を利用していると思います。
これも大学受験、そしてその前の高校受験でも使ったことがあるはずですが、過去問には、出題傾向の把握や弱点の発見、基本の定着など、様々なメリットがあります。
薬剤師国家試験でも、最初過去問を解いた時は難しく感じたものが、今では十分対応できるようになっていることでしょう。
次のフェーズとしては、応用問題への対応です。
これに手を焼く学生は一定数おり、過去問は問題ないけれど応用になるとダメ…という場合は対処が必要です。
【応用に対応できない理由を考察する】

考えられるものを順番にご紹介します。
≪解説の活用方法≫
参考書や問題集には解説がついています、それは過去問も同じ。
過去問は解いて終わりではなく、なぜそうなるのか、その解説をしっかり読んで理解することが重要です。
これをしないと、理解の定着が薄くなります。
≪案外、基礎ができていない≫
過去問を解いてある程度点数を取られても、それは問題傾向や流れなどを把握したためだからかもしれません。
応用ができないのには何かの理由があります。
もう一度、基礎力を見直すようにします。
≪アウトプット学習≫
自分の頭で理解して、言葉などで表現できるフェーズ、つまりはアウトプットです。
これは、しっかり基礎が身について全体像として理解している証でしょう。
友人や兄弟でもいいかもしれません、自分の言葉で説明をしてみてください。
暗記だけではなかなか応用には対応できませんが、’’理解しているもの’’ は使えます。
≪イメージではなく視覚的に理解する≫
応用に対応できない人に共通するものとして、知識のつながりが薄いことも挙げられます。
作用部位や代謝経路など、何となく理解するのではなく、点でつなぎ、視覚的に整理をすることで深い理解力になります。
図や比較表などを作成して、目で理解するのがいいです。
自分だけのノートを作成したり、ストーリーで理解していくのもおすすめのやり方です。
【まとめ】
今日は、大学薬学部の学生のために薬剤師国家試験に関する内容をご紹介しました。
当サイトでは、この他にもたくさんの薬剤師国家試験に関する記事を発信していますので、他の記事にもぜひ目を通しておいてください。
また、大学での勉強のやり方やコツなどもご紹介しています。
では、本日も最後までお読みいただきありがとうございました。