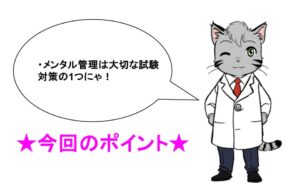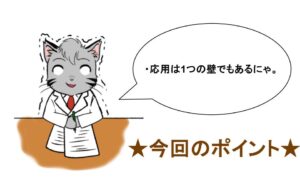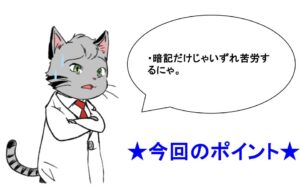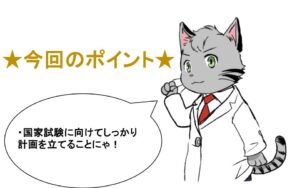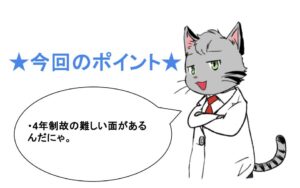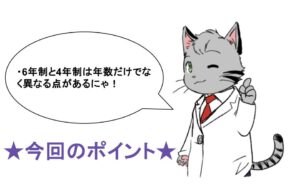【薬学部実習】指導薬剤師との関係がうまくいかない場合の対処法
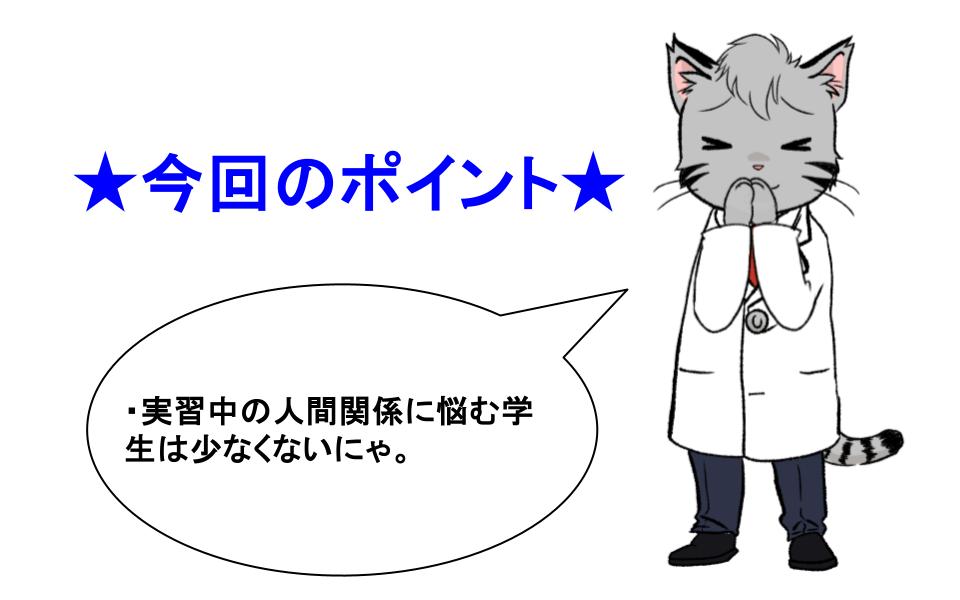
薬剤師になるためには、大学薬学部在籍中に実習に参加しなければいけません。
病院と薬局の2箇所で、合計22週、実習を行うわけですが、そこでは様々なことが起きます。
それは良いことも悪いことも。
今日は、薬学部の学生に向けて、実習で指導薬剤師とうまくいかない場合の対処法についてご紹介します。
ぜひ参考にしてください。
【薬学部実習中のトラブルはよく起きる】
実習では、実際の業務や患者様との関わり方など、多くのことを学べます。
非常に貴重な時間であり、そこで今足りないことや今後の課題などを明確に見つけられることでしょう。
先輩の薬剤師とも関わり、仕事面を含め、経験を伝授してもらうのですが、人間と人間のやり取りですので、トラブルは起こり得ます。
例えば、指導薬剤師からのパワハラや嫌がらせ、実習項目について十分な指導を受けなかったなど、多岐に渡ります。
しかも、その中で、「我慢」を選択する学生が多いのも現実だと思います。
やはり、学生という立場ですし、学びに来ているので、言い返すわけにはいきません。
ただ、我慢はしんどい、それは誰もが思うことです。
学生ができることは限られているかもしれませんが、あります。
【実習中、指導薬剤師との関係がうまくいかない】

いろんなトラブルがある中で、この指導薬剤師との問題はよく聞きます。
いい人に当たれば貴重な時間を過ごせる一方で、’’ハズレ’’ だと実習の内容が薄くなったり、場合によっては人間関係に悩みメンタルなど健康面を崩すことにもなるかもしれません。
学生ができる対処法を順番にご紹介します。
≪自分に矢印を向ける≫
まず最初にやるべきことは、どんなに実習中のトラブルが多いとはいっても、全てが指導薬剤師のせいではありません。
それは当たり前のことで、もしかしたら学生自身が原因になっている場合もあります。
態度が悪かったり、学ぶ姿勢がなかったり、学生自身はまず、こちらに原因はないかを考えます。
もしそこで何か見つかれば、改善して、実習に臨みます。
≪自分の感情を整理する≫
そして、何かいわれて傷ついた…という場合は、その「傷ついた」という感情と「なぜ傷ついたのか」という事実を分けて考えてみましょう。
困っている…のも同じで、「困っている」という感情と「なぜ困っているのか」は別に考えます。
もし自分に非があるのなら、改善するのみです。
感情ばかり先行してしまうと、物事を客観的に見られなくなりますので、注意が必要です。
頭の中で整理できないのならノートなどに書き出してみてもOKです。
≪指導薬剤師の高圧的な態度の裏の意味≫
誰もが高圧的な態度や否定的な態度をとられると嫌な気持ちになります。
人間には感情がありますので、人格を否定された感じです。
でも、高圧的な態度はあなたのことを嫌いなのか、単にその指導薬剤師の性格によるものなのか、判断はしずらいもの。
もし、後者であれば悪気はないので、こちらも深く考える必要はないでしょう。
指導薬剤師の普段の振る舞いや他の人への接し方などを見れば、ある程度わかります。
もう「そういう人だ」、と開き直っていくしかありません。
≪他の先生に間接相談をする≫
その指導薬剤師にダイレクトに話をすると、かえって悪化するかもしれませんので、まずは第三者に相談をします。
現場の他の先生やスタッフの方、大学の教授などでもいいでしょう。
そこで客観的なアドバイスをもらえるかもしれません。
≪相性は仕方がない≫
特に指導薬剤師にも悪気はなく、あなた自身にも問題がない場合は、もしかしたら単に相性の問題かもしれません。
そうなると、正直、もうできることは限られています。
割り切るか、基本的には大学側の判断にはなりますが実習先を変更するかです。
【まとめ】
いかがでしたか?薬学部の実習中のトラブルに対しては、ある程度我慢をすることも大切ではありますが、限度を超えるとそれはマイナスに働くことでしょう。
学びの場、健康を害す場所ではありませんので、その辺りは、自身の状態と相談してベストな選択をしたいものです。
では、次回も大学薬学部に関する情報を発信しますので、ぜひ参考にしてください。