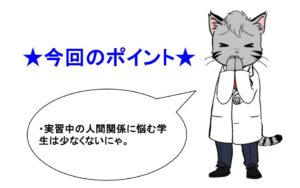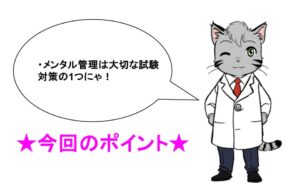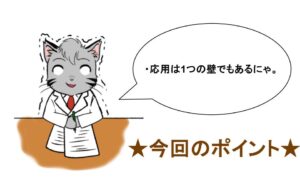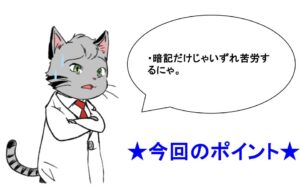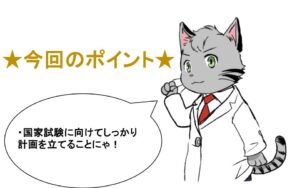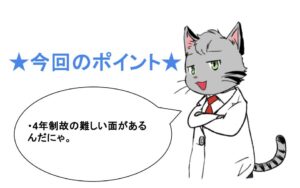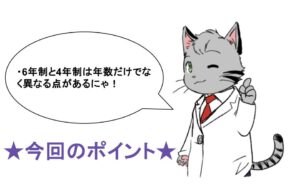【大学薬学部】グループワークをうまくこなすには
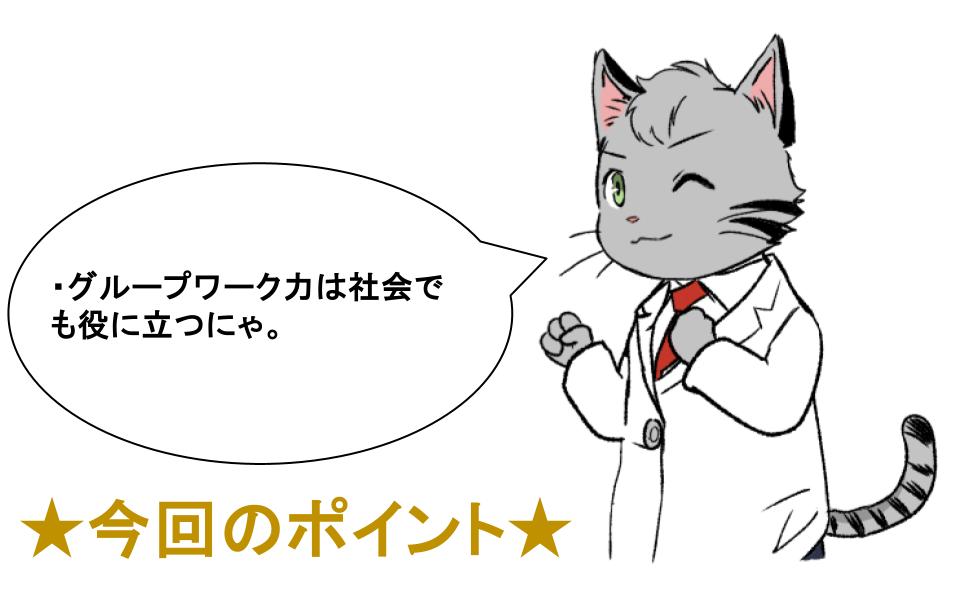
大学に入ると、自分の机に座って板書を取るという作業の他にもいろんな学習形式があります。
その1つにグループワークがあり、これは大学での学びの特徴の代表例でしょう。
加えて、薬学部ではその学問の特性上、このグループワークが多くあり、慣れていない故、苦手意識を持つ人は少なくありません。
今日は、そんな大学薬学部のグループワークに関する内容です。
【大学薬学部のグループワークの目的】
まず、大学薬学部のグループワークとは何かについて見ていきます。
これは、その名の通り、少人数などグループに分かれて指定された課題について話し合ったり、共同で作業を行う授業形式です。
学生個人が座って授業を聞いて理解する通常のものではなく、討論をしたり、共同制作をしたり、プレゼンテーションをしたりといろんな形式で実施されるのがグループワークの特徴です。
薬学部でグループワークが実施される目的としては、下記が挙げられます。
・コミュニケーション能力の向上
・問題解決能力を養う
・協調性の向上
・自己肯定感を高める
・視野を広げる
まず、学生同士が集団になり授業を進めていきますので、他の人とのコミュニケーションは避けられません。
これは薬剤師になってからも同じで、病院で働く場合には医療チームとして医師や看護師らと業務をこなします。
どのような問題があって、どう解決していくか、そのためにみんなで力を合わせて解決策を探すグループワークですので、必然的に問題解決能力も養われます。
自分一人の意見だけでなく、他の人の意見や価値観、視野を聞くことで多角的な視点の獲得にもつながります。
また、そこで自身の意見が採用されたり、貢献できることで自己肯定感の向上にもなるでしょう。
【大学薬学部のグループワーク攻略法】

みんなの前で話すのは緊張する…と苦手意識を持つ人や、話すこと自体はいいけれどどう貢献したらいいかわからない…など、グループワークには慣れていないことで難しさを感じることがよくあります。
それはあなただけでなく、薬学部の学生ではあるあるですので、心配不要です。
大切なのは、グループワークをどう攻略するかです。
≪役割分担が鍵≫
まず、学生みんなが司会のように振る舞えば、当然、うまくまわりません。
テレビ番組で、みんながみんなさんまさんの役割をすると、ボケをする人はいませんし、聞き上手なさんまさん故、話す人がいません。
グループワークでは、まず、各学生が役割を分担します。
その役割に沿って、求められている役目を果たします。
≪発言が活性化する≫
そして、何も発さないとグループワークはまわりません。
恥ずかしい気持ちもわかりますが、グループワークはそういうもの、積極的に発言をします。
間違ってもいいので、何か発することが大切です。
≪感情を優先しない≫
発言をする際に、やってしまいがちなこととして感情に任せることです。
あの人の意見が気に食わないから、反対意見を持っているから、などの個人的な理由で、批判や否定ばかりをするのは建設的ではありません。
相手を言い負かすのが目的ではなく、その議題を解決することに力を注ぎます。
≪傾聴を意識する≫
発言ばかりに気を取られていると、他の人が話せません。
他の学生の声にもしっかり耳を傾けて、多角的な視点を持つことです。
たとえ、間違っている意見でもしっかり耳を傾けます。
≪事前知識を身につける≫
その議題に対して、理解をしていなければ、議論には参加できません。
逆にいうと、理解しているものには自然と発言をできますし、意欲が湧きます。
薬学部で学ぶ内容について、基礎知識をしっかり身につけておくことは、何もグループワークだけでなく学習する上で欠かせません。
【まとめ】
今日は、大学薬学部のグループワークに関する内容でした。
薬学部では学ぶ内容的によくあるグループワークですが、これを苦手とする学生は決して少なくありません。
ぜひ今日の内容を参考に、取り組んでいきましょう。